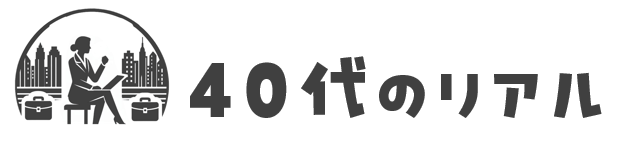親も教えてくれなかった「何のために働くか」という問い
何のために働くのかの問い
3社目の複合機販売会社に転職したときのこと。前職の上場ベンチャーとは違い、伝統的な営業スタイルを重んじる企業で、スーツにワイシャツ、ネクタイ、営業カバンが基本装備だった。私はコピー機の販売だけでなく、新しいITソリューションサービスの立ち上げメンバーとして2期生で入社した。この会社では、ネクタイを緩めたり、靴下が短かったりすると上司から指摘される風土があった。相手が総務部門だったこともあり、身だしなみは特に重要だったのだと思う。
その後、3年ほど勤務すると、組織に大きな改革の波が訪れた。親会社のメーカーが競合に遅れを取ることを恐れ、外部の新しい血を積極的に取り入れる動きを進めた結果、外資系出身の管理職が増え、組織文化も大きく変わった。
そこで、次のような変化があった。
- ノーネクタイ、第一ボタンを開けた統括部長
- 事業部の全体会議(ALL Hands MTG)(通称:オールハンズ)の定期開催
- 販促費の復活
- 営業サポートチームの新設

(※写真はイメージ)
市場が縮小し、販売単価も下がる中で、ITソリューションを売るために、効率化とスピード対応が求められた。上からの指示が厳格に下り、迅速な対応が必須とされ、当時のガラケーの時代に早々とiPhoneが支給されるなど、業務の効率化が進めらた。また、見積もり作業などのルーチン業務を女性中心の営業サポートチームが担当し、営業が本来の業務に集中できる体制が整えられた。
- 統制(上意下達)
- 対応スピード
- 効率化
- 販売(売上増)のために必要や手段の実行(マーケティングを実施し、営業が本来の仕事を実行できる環境で動く
最初は、軍隊かと思った。
統括部長からの短い依頼メールが部長・課長に送られるのだが、送られた数分後には、皆が返信している状態だった。スピード対応できるためにも、他企業がガラケーだった時代にiPhoneに変更されていて、添付書類も難なく見れる環境だ。
こうした改革の背景には、「(身なりよりも)売上を上げることが最優先」という明確な目的があった。しかし、外資系流の評価も導入されたことで、成果を出せない管理職は他部門への異動を命じられることもあり、管理職の間には焦りが生じていた。
ある日のALL HANDS MTGで、統括部長が皆の前で問いかけた言葉が、特に印象に残っている。
「なんのために働くのか」
同僚が指名されて答えましたが、その答えは「給料をもらって生活するため」というものだった。統括部長は「この会社の多くの人がそう答えるね」とだけ言い、その後は特に触れなかった。その場にいた人たちは、その言葉の裏に、「営業が本気で売り上げを上げなければ、給料も得られない」というメッセージが含まれていることを感じていたと思う。
その後、私自身も働き方について考えるようになっていた。
その時期というのが、コロナになる2~3年前になるのだが、
- フルタイム共働きの中、自分の仕事がさらに忙しくなる → 妻の負担が増大
- 子供2人が保育園 → 小学校に入るあたり
- プレイヤー → プレイングマネージメントになる
- リモートワーク化 → フルではないけど、1日アポやチームMTGがない日などは自宅で仕事が仕事できた
共働き(≒子育て)が、当たり前になっていいる中で、「(旧態依然の)男性は出世を目的に一生、同じ働き方をするのはおかしいのではないか。女性も出世しているのは、お子さんがいないDINKSのバリキャリな社会はおかしいのではないか。」とも思うようになってきた。
当然、給料をもらい雇用契約を受けているから安定して生活ができているのも事実である。
一方で、会社でも多様性(ダイバーシティ)の重要性を掲げるようになっていた。
大企業のおける多様性は、人事部門と事業部によりその意味が異なるのが特徴だと思う。「人種・年齢・性別・能力・価値観などの異なるものを受け入れることで、革新的なものやサービスが産み出される」ことであることは、皆同一認識だが、
- 人事部門では、女性管理職比率の向上による多様な働き方や組織運営の変革
- 事業部門では、異業種や異文化による革新的なサービスの提供や効率的な業務の実施
などである。
(結果、上記がうまく回ると、会社としてのアイデンティティが薄れ、各組織が組織ごとのルールができて、チームより意思決定方法が異なり、忙しさが異なり、評価基準も横と比べることが難しくなっている気がする。)
そんな状況の中、マネージャー1回生の時、6人のメンバーのチームを引っ張る中で、わたしの10歳上のメンバーがいた。ちょうど、お子さんが中学受験の年で、彼も熱心だったため、あまり今年度はプライベートの比重を上げてあげたかったり、キャリアで営業職をやりたいとのことで入社し、「残業でもなんでもやりたいので仕事ふってください」というメンバーもいた。営業業務ベテラン勢もいて、新しいジョブチェンジもいた中で、個人の想いをすり合わせたうえで、業務を配分したかった。(数字は達成したが、これは成し遂げれなかった。)
働く理由の共通な理由として、「経済面」はあるにせよ、長いライフプランの中で一生変わらない人もいるが、その時々で変わってもよい価値観。それが現在の働き方の形であるべきだと思う。「子供とのふれあい」、「なにかとなしとげたい」、「評価されたい」、「評価+より給料を上げたい」、「顧客などに与えることで何かを得たい」、「ただ好きなことをしてたい」、「仲間と達成感を感じたい」
自分にとってもそうだし、メンバーにも同じように「いま、何のために働くのか」とうこうことを考えていくことが今後、より重要になるんだと思った。
その後、チームを持つ際には、毎回上記を問うように言っている。
それができる企業が、今後も同じ会社で社員がサステナブルに働けることだと感じていた。